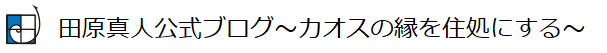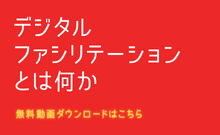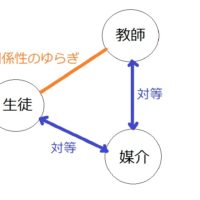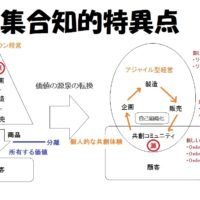コミュニティや共同体という言葉には、束縛やしがらみのイメージがつきまとう。
でも、私が作りたいコミュニティは、束縛やしがらみのイメージとは正反対のものだ。
正反対の2つのものが同じ言葉で語られることで大きな混乱が起きている。
私が作りたいコミュニティの話をすると、私が作りたくないコミュニティのイメージが重なってきて、語るのが難しくなってくる。
そこで、一方に「学習するコミュニティ」、他方に「同調コミュニティ」という名前をつけて区別することを提案してみようと思い、Facebookに次の投稿をしたところ、多くの方がシェアして下さり、コメント欄にたくさんのコメントをいただいた。
それらを踏まえた上で、私が考える両者の違いの表をバージョンアップさせて、次のようにまとめてみた。
| 学習するコミュニティ | 同調(統制)コミュニティ |
| 「絆」を信頼の意味で使う | 「絆」を束縛の意味で使う |
| 「中庸」=ホメオスタシス | 「中庸」=極端ではない |
| 乱を超えて和に至る | 和を乱すなと言う |
| 自由が推奨される | 我慢が強制される |
| 自分でいることが大事 | 適応することが大事 |
| 発達障害がギフテッドと呼ばれる | ギフテッドが発達障害と呼ばれる |
| 思いつきから活動が生まれる | 規則によって行動が決まる |
| 創発的計算によって動く | 手続き的計算によって管理する |
| 集合知による一体感 | 同調による一体感 |
| 和集合で繋がる | 共通部分で繋がる |
| やりながら考える | 誰かの考えに従う |
| フィードバックから学ぶ | フィードバックが出ないようにする |
| 各自が役割を見つける | 既存の役割から選ぶ |
| 場のプロセスを読む | 空気を読む |
| 未来を探る | お互いの腹を探る |
| ドラマが生まれる | 予定通りに進む |
| 創発が起こる | 協同現象が起こる |
| ストレスが癒える | ストレスが溜まる |
| 素人が考え、玄人が実行する | 玄人が考え、素人が従う |
| 直感で行動してから理性で考える | 理性で考えてから行動する |
| 役割は流動的 | 役割は固定的 |
| 対話で決める | 多数決で決める |
| 違和感が尊重される | 違和感が黙殺される |
| 生命論的安心感 | 機械論的安心感 |
| 出る杭は尊敬される | 出る杭は打たれる |
| 外に開いている | 内に閉じている |
| 内発的動機で動く | 外発的動機付けで動かされる |
| 感化によって君子が増える | 同調圧力によって小人が増える |
| 全身で感じる | 頭で考える |
| 分からなくてもやる | 分かることしかやらない |
| 失敗は試行錯誤の一部 | 失敗は責任問題 |
| 興味を持って相手の話を聴く | 自分の判断に基づいて相手の話を聴く |
| 自分の価値基準に従う | 集団の価値基準に従う |
| 色に例えるとターコイズ | 色に例えると赤 |
| フラットな関係 | 縦の関係 |
この中には、私の考えたものもあれば、私のFacebookの投稿に、他の人が追加してくれたものも含まれている。
すっかり悪者にされてしまった感がある「同調コミュニティ」に対する同情の声もあった。
違いをどのように表現するかには、様々な意見があると思うが、違いを区別した上で共に考えるということに大きな価値があると思う。
コメント欄でのやりとりの中で、重要な指摘をいくつもいただいた。
こちらのコメント欄をご覧いただきたい。
やりとりをする中で整理されてきたのは、これらの違いがどこからやってくるのかということだ。
私は、「同調メカニズムも自然の摂理である」という意見に賛成する。その上で、春秋戦国時代の中で孔子が考えたことや、全体主義の台頭に対する反省としてサイバネティクスの創始者であるウィナーが考えたことをもとに考えたい。
ウィナーは、アリやハチといった社会的昆虫に対する考察から、社会秩序はコミュニケーションによって形成されることを見抜いた。アリやハチの社会は、個体間の多様性が小さく同調による自己組織化によって社会秩序が形成される。
私たち人間にも、同調メカニズムが備わっており、同調による協働作業を行うことができる。しかし、人間と昆虫とを分ける大きな違いは、「学習メカニズム」の有無である。
人間は、環境から学習をするため、後天的に多様な個体差を獲得でき、同調によって繋がることだけでなく、違いから学び合うことによって繋がることもできる。後者こそが、人間が新しく獲得した可能性である。
論語では、学習モードを発動させて対話することによって、カオスを乗り越えて調和に至ることができる者のことを「君子」と呼び、同調モードによってのみ他人と繋がることができる者を「小人」と呼んでいる。孔子が考えたのは、人々が君子になれば、学習モードによって社会が調和に至って社会秩序が形成されるということだった。
人間は、状況によって同調モードと、学習モードとを切り替えることができる。10人でボートを漕ぐときは、同調モードを発動させて一体となってオールを漕ぐことができるし、同じ10人で対話を行い、ボートレースの戦略やトレーニングについての集合知を生み出すことができる。
健康なコミュニティは、同調モードと学習モードとが、必要に応じて発動し、協力や学び合いが柔軟に起こるようなものなのではないかと思う。私は、このようなコミュニティを「学習するコミュニティ」と呼びたい。
一方で、何かしらの理由で学習モードが抑え込まれると、人間は、人間であるにもかかわらず、「同調モード」しか発動しなくなってしまうのではないだろうか。私は、このようなコミュニティを「同調コミュニティ」と呼びたい。
つまり、次のようにイメージしている。
・学習コミュニティ→同調モードと学習モードが、必要に応じて発動する
・同調コミュニティ=同調モードしか発動しない
人間が本来持っている「学習モード」が抑え込まれてしまっている状況は苦しく、様々なサインが身体や精神から発せられてくる。このサインを徹底して無視していくと、心身を病んでしまったり、魂に蓋をし、適応するための人工的な自己を蓋の上に作り上げてしまったりするのではないだろうか。
適応するための人工的な自己を作り上げた人たちが集まると、多様性を失っているが故に、同調モードが強力に発動し、同調圧力によって、周りの人の魂を傷つけていく悪循環のスパイラルが回る。ウィナーは第二次世界大戦の反省から、このメカニズムを抽出し、そうならないための方法として「学習に基づいた秩序」というものを考え、サイバネティクスを生み出したのだ。
学習モードの作動を止めないためには、自分の真実に正直になり、言いにくいことを発言していくことが大切だと思う。
隠されている真実を、自分から見にいくことが大切だと思う。
私たちは、同調モードも、学習モードも兼ね備えた人間であり、そのどちらを発動させるのかを自分で決めることができるのだ。