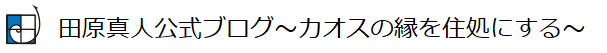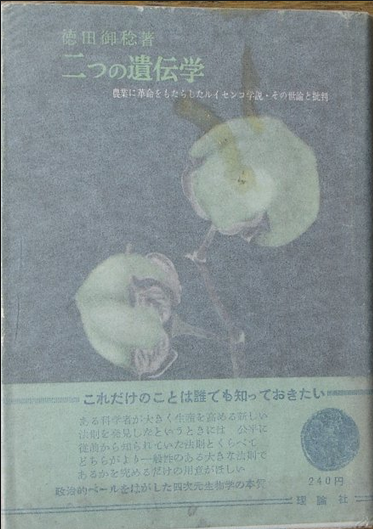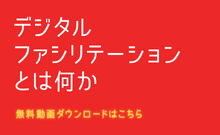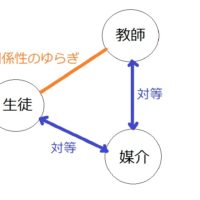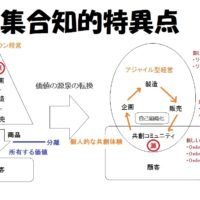農業生物学者から教わったこと(4)
2104年9月に急逝した農業生物学者の明峯哲夫さんから教わったことを書き留めておきたいと思って連載している。
明峯さんは、大学院生時代に学生運動に身を投じた後、大学院を中退し「在野の科学者」という生き方を選んだ。大学院の博士課程3年で中退して予備校講師になり、生き方に迷っていた僕にとっては、「在野の科学者」という生き方は、希望の光だった。在野だからこそできることは何かということをいつも考えていた。
明峯さんが亡くなられた後、遺稿をまとめて出版された『有機農業・自然農法の技術』の第5章 農業生物学を志して には、明峯さんがどんな思いを持って生きていたのかが率直に書き綴ってある。
農業生物学の2つの意味
明峯さんは、自分のことを「農業生物学者」と呼び、自分の肩書を「農業生物学研究室主宰」としてきた。
農業生物学は、明峯さんのアイデンティティだといってよい。
しかし、その実態はどこにあるのだろうか?
明峯さんは、農業生物学についてこのように書いている。
農業生物学っていったい何だろうということなんですが、実態としてはこんな学問はどこにもない。いまだかつてなかったし、これからもおそらくまずないだろうと思います。だけど、農業生物学っていう名称が使われていないわけではない。大げさに言うと、生物学の歴史、あるいは農学の歴史のひとつのアプローチと言ってもいいかもしれません。
実態がない「農業生物学」に、明峯さんは生涯こだわった。いったいそれはなぜなのだろうか?
この本を読んで、はじめてその理由が分かったような気がした。
明峯さんにとって、「農業生物学」という名前との関わりは2つあった。
1つ目は、明峯さんが所属していたのが北海道大学農学部農業生物学科植物生理学研究室だったこと。そこには、「農業生物学科」という名前がついていた。
明峯さんは、大学院生だった明峯さんは、全共闘に加わり、農業生物学という学問はあるのかないのかという議論を教授たちとやったのだそうだ。明峯さんは、
現実にはそのようなものはないのだということを確認することが、僕たちの一つの目的だった。
と書いている。
このとき、明峯さんがどのようなことを考えていたのかは、当時の北大の大学闘争の状況を知らない僕には想像することは難しい。だが、明峯さんは、大きな夢とロマンを持ち、研究者としての道を歩んでいたことは間違いない。それは、この言葉からもひしひしと伝わってくる。
大学院生のころ、僕は生理学あるいは生化学という分野に身を置いて、細胞レベルで、ある細胞にある環境条件を与えるとその細胞がうまく環境に適応していくように振る舞う具体的な様子と仕組みを、細胞レベルあるいは物質レベルで調べたいと思っていました。ぼくが研究者としてとどまるのであれば、これをライフワークにしたいと思っていました。でも、それは潰えたわけです。
これは、全くの想像だから間違っているかもしれないが、明峯さんは、「大学で農業生物学を研究すること」が、日本のヒエラルキー構造の中に組み込まれて存在することに真剣に向き合ったのではないかと思う。
1970年代に国が農学部に求めていたものは食糧増産であり、国から研究費を支給されている大学の研究者は国の意図から離れてどれだけ自由にやれただろうか。
20世紀の大量生産型の農業を推し進めるための学問が求められる中で、学問的に独立した「農業生物学」というものは存在し得るのだろうか。
明峯さんは、自らの大学闘争を次のように総括する。
1960-70年代にかけては、まだ緩やかな時代でした。科学は自由にできるんじゃないかというようなことが、まったくなかったわけじゃない。しかし、そんなことは幻想だと考えて、アカデミズムにいることは潔しとしないというふうに、僕たちは総括することになります。
明峯さん、実際には存在しなかった自由な科学としての「農業生物学」というものを思い描き、それを自分のアイデンティティにしたのだと思う。
もう1つは、旧ソビエトの生物学者、ルイセンコが1954年に出版した本の名前である『農業生物学』。
ルイセンコは、ヘーゲル哲学の弁証法を生物進化の原理に据え、共産主義のイデオロギーに基づく独自の生物学を創り上げた。
生物が環境にどのように適応していくのかということに強い関心を持っていた明峯さんが、ルイセンコに惹かれるのは、自然なことだったと思う。
しかし、一方で、ルイセンコは、スターリンやフルシチョフのもとでソビエトの国家権力の中枢に座り、ルイセンコに反対してメンデル遺伝学ニコライ・ヴァヴィロフを「ブルジョア的エセ科学者」と非難して逮捕、獄死させたということでも有名であり、獲得形質遺伝を唱えたことで、メインストリームの生物学から疑似科学の烙印を押された人物である。
学会などで、「ルイセンコ生物学」の話を持ち出しようものなら、エセ科学者のレッテルを張られてしまうことを覚悟しなくてはならないだろう。
だから、
ぼくはルイセンコの学説に、学生時代にものすごく惹かれました。ルイセンコは戦後まもなく、僕らの父親の世代にいろいろと議論され、ぼくはそれから15年経った後の世代なんですが、すごく惹かれたのです。
というように、ルイセンコのことを肯定的に語るのは、実は、とても勇気の必要なことなのだ。僕は、この本を読んで、こんなにはっきりとルイセンコについて書いてあることに驚いた。明峯さんは、自分の信念について語る上で、大きな影響を受けたルイセンコについて語らずにはおられなかったのだろう。
僕は、予備校の講師室で明峯さんから表紙がボロボロになった本を渡された。それが、明峯さんにとって大切な本だということはすぐに分かった。
それが、僕とルイセンコとの出会いだった。ルイセンコの言葉は、僕の心にも響いた。明峯さんの言葉を引用する。
ところが、ルイセンコは遺伝子の存在を否定している。つまり、細胞全体が遺伝子であり、核の中にある小さな遺伝子みたいなものに細胞が牛耳られるはずがないと。細胞全体あるいは生命体全体が遺伝子的働きをする主体であって、したがって細胞や主体全体に環境がある一定の影響を及ぼす。遺伝子が変化するのではなくて、細胞全体あるいは生命体全体が環境にすり寄っていくということなんだと彼は言う。
そして、ルイセンコの言葉に対して、明峯さんは、「ぼくなんかは今でもそう思っています」と述べる。明峯さんは、ソヴィエト生物学、あるいはルイセンコ農業生物学全体を支持するわけではないが、ルイセンコが夢想した生命観はこれからの時代に有効性があると述べる。
明峯さんの「農業生物学」には、ルイセンコが夢想した生命観、つまり、生物と環境が一体となってなじみ合うという生命観も含まれているのだと思う。
エピジェネティクスが出てきて状況は少し変わったが、少し前までは、公の場で獲得形質遺伝を肯定したり、ルイセンコを肯定したりすることは、学者としての「死」を意味していたといっても過言ではない。
でも、明峯さんの心の中では、ルイセンコの言葉が強く響いていて、それが、明峯さんの中で葛藤を生み出していた。
「いつか、ルイセンコについてはまとめなくちゃいけない。」
と、何度も言っていた。
明峯さんは、このように書いている。
農業生物学というのはそういう世界(植物が環境にだんだんなじんでいき、それが種子によってつながれていく世界)を表現する言葉でもあったのです。ルイセンコが『農業生物学』という教科書で書いた世界は、現在ではほぼ否定されていて、正統的な生物学者からはほとんど無視されている状態にあります。いまだにルイセンコに後ろ髪をひかれているのはぼくひとりくらいかもしれないし、いずれにしても少数派です。
この本を読んで、明峯さんは、ルイセンコについて、ちゃんとけりをつけたんだなと思った。
だから、僕自身も10年以上かけて、明峯さんとの対話を通して考えてきた獲得形質遺伝についての自分の仮説を書く。
信じていることを率直に表現していくことは美しいということに気づいたから。
情報はどこに蓄えられるのか
生物は、情報をどのようにして蓄えるのだろうか?
記録装置をデータとプログラムに分け、データをマシンが読み取ってプログラムが動くというのがノイマン型コンピューターであり、細胞はノイマン型コンピューターとのアナロジーで理解されることが多い。
DNAがデータを格納しているテープであり、mRNAやリボソームがそれを読み取ってタンパク質を合成し、タンパク質が細胞内のプログラムとして機能を発現させていくというようにである。分子生物学が作りあげた細胞のイメージは、まさに「機械」を想起させるものだ。
これは、むしろ当然かもしれない。19世紀以降、機械論的世界観のパラダイムによって科学は進んできており、生物を機械論的世界観に基づいて、いわば、分子機械として理解しようとする試みが分子生物学だからだ。その結果として浮かび上がってくる生物像は、当然、「機械」のようなものであろう。人間は見たいように見るからだ。科学も時代の精神に大きく制約されているのだ。
しかし、生物は一方で自律分散システムであることを忘れてはいけないと思う。
多細胞生物の細胞は高度に機能分化しているが、もとは、一つの受精卵から分裂したものであり、すべての細胞が同じDNAを持つ。
同じDNAを持つ細胞群が、相互コミュニケーションにより役割分担を決め、機能分化していくのだ。
機能分化した後の構造を見て、「機械」とのアナロジーで理解することは可能かもしれないが、生物は、環境に応じて異なる構造を創り上げる。明峯さんの言葉を借りれば融通無碍な存在なのだ。「機械」として理解しようとすると、生物の融通無碍な部分が抜け落ちてくる。
情報を記録する器官といえば、なんといっても脳であろう。
脳は興奮性素子であるニューロン細胞が集まっているネットワークである。ニューロン細胞が相互作用を行う中でマクロな時空間パターンが生じるようになり、それによって機能分化が起こり、緩やかな機能の局在が起こる。
脳の一部が損傷すると、それによって、手足の麻痺が起こるなど、特定の機能が損失する。それを、機械論的な見方で解釈すると、その損失した箇所に「手足を動かす」という情報が蓄えられているということになる。その考えを極端にしたものが「おばあちゃん細胞」である。おばあちゃんの記憶をコードしている細胞(または、細胞群)があって、その脳細胞が死ぬことがおばあちゃんを忘れるということに対応するという考えである。しかし、脳の一部が損傷しているのにもかかわらず、他の部分が補完的に働き機能を回復するということも起こる。生物は融通無碍な性質を発揮するのだ。
コンピューターの発達により、脳の一部を壊して機能の損失を調べる以外の方法が可能になった。ニューラルネットワークをコンピューター上に作り、構成論的に脳を理解する方法である。ニューラルネットでは、外部からの入力と出力をネットワークで結び、評価関数によって評価しながら、ネットワークの結合強度を少しずつ変化させていきネットワークを最適化していく。ニューラルネットワークにおいて情報はどこに蓄えられるのだろうか?特定のニューロン素子では決してない。ネットワークの結合強度分布全体に情報が練りこまれているのだ。
これは、言語習得についての議論を思い起こさせる。文法は生得的に獲得されているのか、それとも、後天的に獲得されるのかという議論だ。この問題対してエルマンは、エルマンネットというニューラルネットワークを組み、「次に来る語を予想する」という問題に対する学習を行った。ある程度以上のデータを用いて学習を行った後、ネットワークは、次に来る語を予想するようになったが、驚いたことに、主語の後に予想される語群は動詞や助動詞であるというように、あたかも文法を獲得したかのような振る舞いを見せた。では、文法の知識はどこにコード化されているのか?ニューラルネットの一部のニューロン素子を取り除けば、ネットワークは文法の知識を失うだろう。では、そのニューロン素子に「文法知識」がコードされていたのだろうか?そんなことはないだろう。文法知識は、ネットワークの結合強度を少しずつ調整していく中で、ネットワーク全体の機能として獲得されたのだ。
ネットワーク学習をするのは脳細胞のような神経細胞だけではない。体細胞もネットワーク学習をする。粘菌細胞は、興奮性を示し、流動的に形を変えることでネットワーク構造を変化させる。情報系と力学系とが相互に影響し合っているのだ。脳細胞が電気パルスを通して情報のやり取りをするのに対して、粘菌細胞は化学物質の濃度の波を通して情報のやり取りをする。しかし、どちらも興奮性を示す素子であり、情報のやり取りに応じてネットワークの構造を変化させていくという点では同じである。
2008年、当時、北海道大学で研究していた中垣俊之さんは、粘菌の情報処理能力の研究を行っていた。中垣さんは、粘菌のネットワークが迷路を解いたり、記憶を保持したりすることができることを示した。参考記事はこちら これは、粘菌の形態形成の数理を研究していた僕にとっては全く驚くことではない。なぜなら、粘菌のシミュレーションに使われる興奮性の数理モデルは、ニューロンの研究から見つかったものと同じものを使っていたからだ。数理モデルのレベルでは、脳と粘菌の間には、大きな違いがなかったわけで、脳と粘菌とのアナロジーを最初から意識しながら研究していた。
中垣さんの研究では、粘菌細胞は、周期的な環境の温度変化を記憶する。この記憶は、多核単細胞である真正粘菌のどれか1つの核にコードされているのだろうか?そんなはずはないだろう。粘菌細胞の形、つまり、ネットワーク構造の中に練りこまれているはずだ。
このように考えていくと、「生物は、ネットワークのつなぎ方を少しずつ変えながら、ネットワークの中に様々な情報を蓄え、必要に応じてそれを使っていく」ということを生物の原理に据えたくなってくる。
神経ネットワークも、体細胞ネットワークも、その原理に従っているように見える。
では、遺伝子ネットワークはどうなんだろうか?
遺伝子の機能を調べる方法は、「ノックアウト」という方法である。特定の遺伝子を壊したときに、どんな機能が失われるのかを調べ、遺伝子と機能とが一対一に対応しているという前提のもとに、その遺伝子に「●●遺伝子」という名前をつけていく。
ある遺伝子を破壊したマウスが肥満傾向を示したら、その遺伝子を「肥満遺伝子」と名付けるというような具合である。
これは、脳の一部を損傷したときに失われた機能と、その損傷部位とを1対1に対応させたのと同じロジックであるが、脳においてはすでにそのロジックは崩れている。
細胞内の遺伝子を含むネットワークも学習しているのではないか?
学習によって獲得された知識はどこに蓄えられるのか?
それは、遺伝子のように局在するものではない。たとえその部分をノックアウトしたときに特定の機能が失われたとしても、それは、その機能がその遺伝子にコードされていることを意味しない。福岡伸一が『動的平衡』の中で述べたように、別のルートが現れて、失われた機能を補うといったような融通無碍な性質を、生物はここでも見せるのだ。
学習した情報は、ネットワーク全体の結合強度分布に練りこまれているのではないか?
だとしたら、ネットワークの結合強度分布を調整している非コードDNAの発現調整こそが重要であり、それを担っているエピジェネティクス情報、つまり、DNAメチル化の分布などがネットワーク学習を反映しており、学習成果をエピジェネティクス情報として次世代へ受け継いでいくことが、獲得形質遺伝なのではないか。
もう少し詳しく説明しよう。
DNAには、タンパク質をコードしている領域と、コードしていない領域がある。タンパク質をコードしていない領域は大野乾によってジャンクDNAと名付けられたが、近年になり、その領域が果たしている役割が明らかになってきた。そこには、タンパク質に翻訳されないRNAがコードされていて、そのRNAが転写調節など、様々な役割を担っているということが分かってきたのだ。
高等生物になるほど、非コード領域が豊かになっていく。この部分を複雑化させていくことで、システムを複雑化させていったように見える。
DNAにコードされた情報のすべてが発現するわけではない。DNAの表面には「メチル基」などの蓋があり、その蓋がどこについているかによって発現する箇所が変わってくる。DNAメチル化などDNAを修飾しているものをエピジェネティクスと言う。同じDNAであるのにもかかわらず細胞が違った性質を示すのは、エピジェネティクス情報が異なるからである。
エピジェネティクス情報は、環境との相互作用によって変化し、それによって細胞の環境応答の仕方が変わってくる。エピジェネティクスは環境との相互作用で変化するのだ。ES細胞と分化した細胞との違いもエピジェネティクス情報の違いであるから、iPS細胞のようにうまい条件を見つけてエピジェネティクス情報を書き換えてやれば、ES細胞を作ることも可能である。
そして、このエピジェネティクス情報は、植物においても、動物においても、次世代に受け継がれることが実験によって確かめられている。つまり、その生物個体が環境とのやり取りをする中で刻んだエピジェネティクス情報が、次世代に伝わるのだから、これは、獲得形質の遺伝に他ならない。
エピジェネティクスは、多くの非コード領域の発現に関わっているのだから、細胞内ネットワークの結合強度分布の調整に関わっているはずだ。
細胞内ネットワークが環境とのやり取りの中で「ネットワーク学習」した結果が、エピジェネティクス情報としてDNA表面に刻まれ、それが次世代に受け継がれていくというのが、僕が考えていることだ。
これが、明峯さんとの対話の中から、「在野の研究者」として、10年以上かけてたどり着いた獲得形質遺伝についての僕の仮説だ。
結果として、ルイセンコの言っていたことに近づいてきた。
細胞内の反応経路は日進月歩で明らかになり、その情報はデーターベース化されている。そのビッグデータを使って様々な情報を取り出すバイオインフォマティックスという分野も生まれている。さらに、それらをシステムとして組み上げるシステム生物学という分野も生まれている。
その中で、細胞内のネットワークがどのような振る舞いをしているのかが検証されてくるのではないかと思う。
遺伝子は、もしかしたらシステムの中でレバレッジが効く位置を占めているのかもしれないが、それは、システムがあってこそ意味を持つ。
1対1対応は言語によって理解しやすい。それに対して、ネットワーク学習は言語による理解を拒む。だが、理解しやすいことが真実だとは限らない。
※タイトルの絵は、明峯さんのスケッチ。こちらからお借りしました。