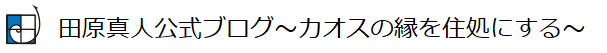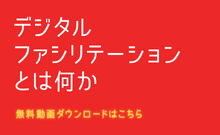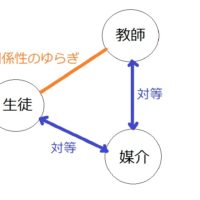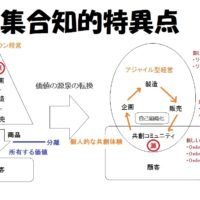農業生物学者から教わったこと(1)
2014年9月に亡くなった農業生物学者の明峯哲夫さんの本が届いた。
実は、これまでに明峯さんが書いた原稿を、たくさん読んできた。同じ予備校で10年間、一緒に働いていて、講師室でプリントアウトした原稿を渡されて感想を求められることが多かったからだ。明峯さんの原稿を読んで、それをもとに話し合うのは、僕にとって楽しみなことだった。
でも、今回、この本を読んで、断片的に聞いてきた明峯さんの考えの全体像が見えてきた。これまでに話してきたたくさんのことの背景が見えてきて、改めていろんな気づきがあった。それだけじゃなく、最後に話してから数年の間に、明峯さんの思考は進化し続けていた。たぶん最近考えたんだろうと思われることもたくさん書いていった。
最初は、本のレビューを1つの記事で書こうと思ったが、本を読んだら、明峯さんとのいろんな思い出がよみがえってきてしまった。それは、僕にとって本当に大切な思い出なので、ここに書き綴っておきたい。
話は、脈絡なくあちこちに飛ぶと思うが、ときどき、本の内容に戻ってこようと思う。ちょっと長くなりそうなので、記事のタイトルに番号をつけた。何回かの連載になると思う。
植物が植物を育てる
この本の第1章は、
第1章 植物成長の原理 ― 植物が植物を育てる ―
というタイトルである。これは、生命の自己触媒的なプロセスを原理に据えていることを意味している。
大学院で複雑系や自己組織化現象を研究し、自己組織化の頂点として生物の自己組織化を研究テーマに選んだ僕にとっては、生物は自己触媒的なプロセスによって自己組織化する存在である。
だから、明峯さんの本の最初の一文
「農業は謎に満ちた営みです。生命の複雑系です。分からないことがたくさんあります。」
という言葉には心の底からうなづける。
この言葉は、機械論的世界観に基づいて推し進められた工場経営のような農業に対するアンチテーゼだ。植物を一定のインプットに対して一定のアウトプットを返してくる単純な機械のようなものだと見なし、周りと隔離した孤立系における実験結果を積み重ねて「理解した」と言い切る20世紀型の科学的アプローチに対して、そうじゃないと主張しているのだ。
単純なインプットーアウトプット系として植物を捉える代わりに、明峯さんが原理に据えたのは、
(1)植物は自然に育つ
(2)植物を育てるのは植物だ
(3)その秘密は土の中の有機炭素蓄積にある
の3つ。
最初の原理は、人間から農作物と名付けられている植物も生き物だという主張だ。進化の中で、人間の手を借りなくても生き物として育つことのできる力を持っているということに立ち返って、その力を引き出していこうということだ。
次の原理は、植物は生態系ネットワークの中で共生的に生きているということだと思う。生態系ネットワークが豊かに育っていくことで、ネットワークに加わっているすべての生き物が栄えていくということなのではないだろうか。
3つ目の原理は、栄養である窒素化合物と作物との2者の関係で捉えるのではなく、窒素と炭素循環系を含む土壌生態系をシステム思考的に考えたときに、明峯さんは、有機炭素がスターター、または、アクティベーターとして働き、土壌生態系のサイクルが回りだすということを主張する。これは、農業の教科書とは異なる見解なのだそうだ。
複雑系を学んできた僕にとっては、このような考え方は、とてもなじみがあるものだ。
自己組織化の原理は、非平衡開放系において正のフィードバック(自己触媒的なはたらき)が起こることだ。
アクティベーターがわずかな揺らぎを増幅させて構造化していき、やがて、インヒビターがその動きを抑えて定常状態になり、次第にインヒビターの働きが強くなっていって減衰していくというサイクルが1回きりで終わる場合もあるし、振動的に反復するときもある。この系を含む、もう一階層上の上部システムが、より遅い周期でサイクルを回し、上部サイクルと下部サイクルとは相互に影響し合う・・・。これが、自己組織化的な世界観だ。
このような観点から植物の世界を見ると、1年草が短いサイクルを繰り返す一方で、森林系などの上部システムがゆっくりとしたサイクルで動いているように見える。
すべては相互に密接に関連していて、複雑にネットワーク化している。その中の2つを取り出して2者の関係として論じることに意味がない。
複雑に張り巡らされたネットワークの一部を変化させたときに、ネットワーク全体がどのような影響を受けるということを予想することはほぼ不可能なのだ。
20世紀型の科学的な知は、理想的な環境を周りから隔離することによって得られるものだ。しかし、隔離した外側にも自然があり、隔離するという行為によってネットワークは影響を受ける。それを無視することによって20世紀型の科学的な知は成り立っている。
そのようなあり方に対するアンチテーゼを掲げて、明峯さんは、新しい農業のあり方を第一原理から再構築しようとしている。
第一章の一行目から、明峯さんの想いが溢れている。
在野の研究者としての生き方
大学院の博士課程を中退して予備校講師になったころ、僕は、何を目指して生きていけばよいのかが分からなかった。
物理学の世界で研究者になるというのは、子どものころからの夢だったし、それが叶う寸前まで来ていた。
でも、同時に、科学が持つ傲慢さや、社会に存在するヒエラルキーに気づくようになり、子どものころのような無邪気な気持ちで物理学の研究者を目指すことも出来なくなっていた。
僕が予備校の講師室で明峯さんと出会ったのは、そんな迷いに迷っていた時代だった。
僕から見た明峯さんは、いつも凛としていた。
いつも農業や生命についての本質的な問題について考えていて、一歩一歩前へ進んでいた。その姿に、どれだけ勇気づけられたか知らない。
環境が変わったからと言って、考えるのをやめずに、自分にとって本質的な問題を考え続けようと思えたのは、明峯さんの影響が大きかったと思う。
アカデミックな世界で上を目指していくのではなく、自分独自の道を切り開いていこうと覚悟を決めることができた。
僕が、研究の場を離れても、ずっと興味を持ち続けているのは「生命らしさとは何か」というテーマだ。
テントウムシを指に這わせると、上向きに向かって歩く。
指の向きを変えると、テントウムシも歩く向きを変え、常に上向きに向かって歩く。
この部分を切り取ると、「上向きに向かって歩くというルールに従っている機械」のように見える。
しかし、指先まで到達したテントウムシは、それ以上、指を上ることが出来なくなり、前足をパタパタさせて困った状況に陥る。ルールが適用できなくなったからだ。
テントウムシが単なる機械ならこれで終わり。でも、テントウムシは生き物だ。ここで、それまで従っていたルールから抜け出し、飛び立つのだ。
僕は、ここに生き物らしさを見る。
生き物は、環境の袋小路に陥ると、生きるためにありとあらゆる可能性を試してもがく。そして、飛躍する。
それは、edge of chaosのイメージと重なり、僕をずっと引きつけている。
そして、そのイメージは、環境の袋小路に陥った自分自身を支えてくれ、そこから抜け出して新しい芽を出していくことができた。
これは、全くの想像だけど、明峯さんは、全共闘に加わって、大学院を中退してアカデミックな場から去ったときに人生の袋小路に入ったのだと思う。そして、そこから、農業生物学者という独自の生き方を見つけ、独自の道を切り開いていったときに、自分自身の「生命らしさ」を感じたんじゃないかなと思う。
明峯さんも、僕と同じ「生命らしさ」に僕以上にこだわり続けていて、植物が、農作物として受動的で無力な存在だと見なされることを徹底的に拒否してきたし、自分自身を外から定義されるのを拒んで自分の人生を生きることにこだわってきたから、きっとそうなんじゃないかなと思う。
生命を語るときに、袋小路に陥ってもあきらめずに、そこから芽を出して、飛躍していくという側面を抜かすことはできない。
それこそが、機械と生命とを隔てるもので、機械と自分自身とを隔てるものだからだ。
人間は社会や学校から様々な情報をインストールされて作られる。でも、そこから抜け出して、情報をインストールした側の意図を超えて、様々な芽を出し、花を咲かせることができる。
明峯さんが植物に投げかける目はとても優しい。そして、それは、予備校の生徒に投げかける目と全く同じだ。
生命は、常に暴走し、逸脱する可能性を内に秘めている。
いざとなったらやれる存在。
機械とは違う。
※タイトルの絵は、明峯さんのスケッチ。こちらからお借りしました。